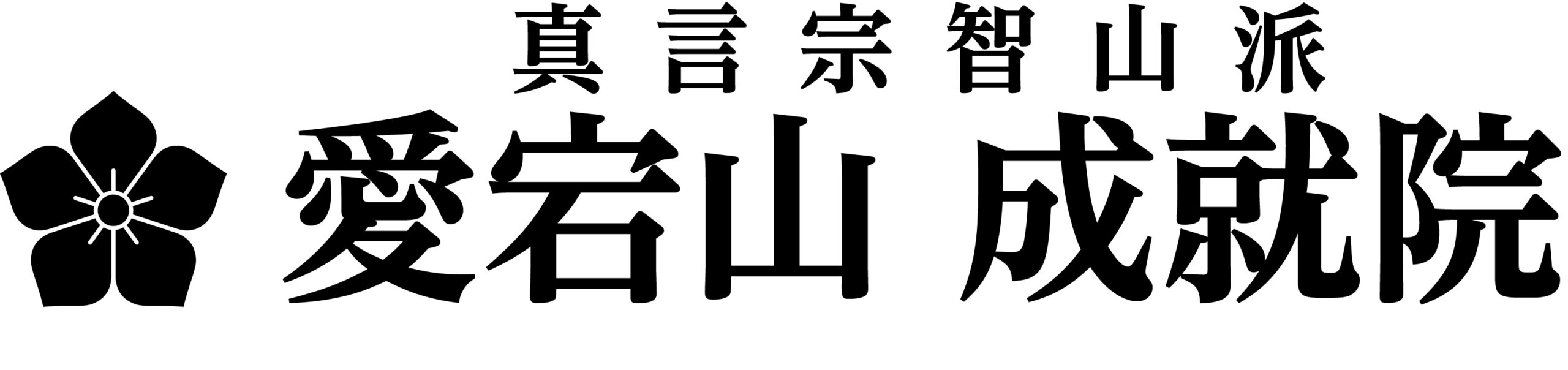JOJUIN
成就院
當山は愛宕山成就院と称し真言宗智山派、京都東山七条の総本山智積院の末寺である。
寺伝によると弘仁11年(820年)真済僧正により開創される。慶長12年に順清和尚の中興開山により、阿弥陀堂、不動堂、閻魔堂等の、粕壁随一の諸堂伽藍を誇ったと伝わる。
慶応2年(1866年)の火災により、堂宇並びに文献、什物等悉く灰燼に帰す。以降久しく荒廃する。明治、大正、昭和初期にかけて30世寛如和尚、31世隆新和尚らが再興の種子を蒔き、32世大僧正隆秀和尚により本堂、客殿、仁王門の建立、墓地整備拡充など、次々と大浄行が開花成就する。令和6年には大日堂曼荼羅堂建立により、さらなる伽藍充実を成す。諸堂内には寺宝の仏像20数尊がお祀りされている。
年間行事
3月 春彼岸
8月13日~15日 盂蘭盆会
8月16日 大施餓鬼会
9月 秋彼岸
11月 お月見コンサート(休止中)
※現在は休止中ですが、毎月第二日曜日に阿字観(瞑想会)を開催しています。
SHINGONSYU
真言宗
真言宗(しんごんしゅう)は、日本の仏教の一つで、密教(みっきょう)という特別な教えを中心とした宗派です。これは、弘法大師(こうぼうだいし)空海(くうかい)というお坊さんが、約1200年前に中国から学び、日本に伝えました。
簡単に言うと
真言宗は「密教」と呼ばれる深い教えを実践する宗派です。この「密教」というのは、普通のお経や教えを学ぶだけではなく、秘密の教え(密意)を通して悟りを目指すものです。
主な特徴
- 曼荼羅(まんだら)
曼荼羅という絵を使って、宇宙や仏の世界を表現します。特に、「胎蔵界曼荼羅(たいぞうかい)」と「金剛界曼荼羅(こんごうかい)」という2つが有名です。 - 真言(しんごん)
「真言」とは、仏や菩薩を称える短いお経(マントラ)のことです。これを唱えることで仏とつながると信じられています。例えば、有名な真言に「オンバザラダドバン」や「オンアボキャベイロシャノウマカボダラマニハンドマンジンバラハラハリタヤウン」などがあります。 - 手と体の動き(印相:いんそう)
手で特別な形(印)を作ったり、身体を使った動作をすることで、仏の力を取り入れるとされています。 - 大日如来(だいにちにょらい)
真言宗の中心的な仏様で、宇宙そのものや真理を象徴する仏です。 - 悟りへの道
真言宗では、修行を通して生きたまま「即身成仏(そくしんじょうぶつ)」、つまり仏になることを目指します。
実際に何をするの?
- お寺での修行や儀式
真言宗のお寺では、護摩(ごま)と呼ばれる火を使った祈りの儀式や、般若心経(はんにゃしんぎょう)を唱えるお勤めがあります。 - お守りや祈願
真言宗は現世利益(げんぜりやく)、つまり今の人生を良くするための祈りも大切にします。
簡単な例え
真言宗は、仏教の中でも「特別な方法」を教えてくれる道場のようなものです。先生(空海)が書いた教科書(経典)やマニュアル(曼荼羅)を見て、特別な言葉(真言)や動き(印)を使いながら、宇宙の真理に近づく修行をする、そんなイメージです。
CHISANHA
智山派
智山派(ちさんは)は、真言宗の一つの流派で、日本における密教の伝統を大切にしながら、修行や仏教の教えを伝えている宗派です。真言宗にはいくつかの派があり、智山派はその中で特に弘法大師空海の教えを基盤としながら発展しました。
簡単に言うと
智山派は、真言宗の教えを「より多くの人に分かりやすく伝え、現代社会でも役立つ形で実践する」ことを目指している宗派です。真言宗の伝統である密教を中心に、護摩(ごま)の儀式や祈りを通して人々の幸せや平和を祈ります。
主な特徴
- 総本山(そうほんざん)
智山派の中心となるお寺は、京都にある**智積院(ちしゃくいん)**です。このお寺は、豊臣秀吉ゆかりの寺院としても知られ、美しい庭園や建物があります。 - 護摩(ごま)の儀式
護摩とは、火を使った祈りの儀式で、煩悩(悩みや迷い)を焼き払い、願いを仏様に届けるとされます。智山派の僧侶たちは、この護摩をとても大切にしています。 - 学問と教育
智山派では、密教の教えを学ぶための教育にも力を入れています。特に僧侶の育成や、仏教の教えを学べる学校の運営に熱心です。 - 地域とのつながり
智山派のお寺は地域との関係を重視し、祈りやお祭り、講話などを通じて地元の人々との交流を大切にしています。 - 現代社会への適応
密教の深い教えを現代にも活かせるよう、祈願や法話を通じて、日々の悩みや心の安らぎをサポートしています。
実際に何をするの?
- 祈願や法要
智山派では、家内安全、商売繁盛、健康祈願など、さまざまな願いを込めた祈祷を行っています。 - 地域イベントへの参加
多くの智山派のお寺では、地域での行事やお祭りに積極的に参加し、人々に仏教の教えを身近に感じてもらえる活動をしています。 - 観光地としての役割
智積院をはじめとするお寺は、美しい庭園や文化財を有しており、観光地としても多くの人々に親しまれています。
SHICHIFUKUJIN
七福神
**七福神(しちふくじん)**は、日本で幸せや繁栄をもたらすと信じられている7人の神様のことです。それぞれが異なる福(幸運や利益)を象徴しており、正月や縁起の良いシンボルとして親しまれています。
七福神のメンバーと役割
大きなお腹と笑顔が特徴で、袋を背負っています。
恵比寿(えびす)
唯一の日本由来の神様で、商売繁盛や漁業の神様。
魚(鯛)や釣り竿を持っている姿で描かれます。
大黒天(だいこくてん)
富と食物を司る神様。
打ち出の小槌(願いを叶える道具)と大きな袋を持っているのが特徴。
毘沙門天(びしゃもんてん)
戦いの神であり、厄除けや勝負運を守る仏教の神様。
鎧をまとい、宝塔や槍を持つ勇ましい姿。
弁財天(べんざいてん)
芸術、音楽、学問、財運を象徴する女神。
琵琶(楽器)を持つ美しい女性として描かれます。
福禄寿(ふくろくじゅ)
長寿、幸福、財運を司る神様。
長い頭と白い髭が特徴的。
寿老人(じゅろうじん)
長寿の神様で、健康や平和を象徴。
亀や杖を伴った穏やかな老人として描かれます。
布袋尊(ほていそん)
大らかさや満足感、子どもの守護神。

成就院大日堂納骨壇
所在地/埼玉県春日部市粕壁3-9-28
アクセス
春日部駅 東口徒歩5分
専用駐車場有り
注意事項
- 事前にお電話でご予約の上、ご見学ください。
- 葬儀・法要中などで電話に出られない場合がございます。